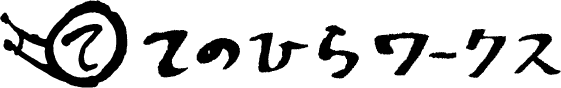おかやま希望学園のこと/3月5日
私たちが多聞をのびのび小学校に転校を促したのは
多聞の自発性や生きる力を伸ばせるのではないかと考えたからでした。
生きる力とは、私たち親以外にも頼れる力であり、頼れる人やモノやコトを獲得していく経験を積んでほしいという願いがありました。
就学するときに通常学級は難しいと考えていた私たちは
支援級の選択肢以外に特別支援学校も真剣に検討していました。
出生時に脳性麻痺というハンディをもち、重度の脳障害の可能性を診断されていたこともあり、
就学前までゆっくりすくすくと育ってくれたことだけでも奇跡的なことだと感じていましたが、
これからはより社会性を求められ、学業でも成績という相対評価がずっとつきまとうことを考えると、
これから通う義務教育に不安しかありませんでした。
しかし私たちの不安は杞憂にすぎませんでした。
地元小学校の知的支援クラスと交流クラスを柔軟に行き来しながら、
丁寧に温かく先生方に見守られ、上級生にも弟のように可愛がられ、仲間意識の高い同級生たちにも恵まれました。息子にとって素晴らしい時間だったと思います。
以前の小学校の就学前に担任の先生から「Tくんにはこれからの6年間でどんなふうに成長してほしいですか?」と聞かれたときに、
「自分の足で学校に行き、自分の足で家に帰って来てくれたら、満足です。」と答えたましたが、それ6年どころか3年もかからず、その願いは叶ったのでした。
おまけに友達が遊びに来てくれたり、友達の家まで遊びに行けるようになったり、息子はそのあたたかな環境の中ですくすくと成長しました。
ここで私の中にさらなる欲が生まれます。のび小への転校です。
のび小への転校を考える際に、別の学校もいろいろ調べましたが中でも一番興味をもったのは「きのくにこどもの村学園」でした。
こどもといっしょに見学もしましたが、「よしここで!」という雰囲気になりませんでした。多聞も同じでした。
家族ごと引っ越さなくてはならないなどの理由から現実的にも難しく、そもそも高いハードルなのは承知のうえででしたから、
それを乗り越えようと思えるほど、それほどのどうしても行きたいという熱量が必要でしたが、そこまでには至りませんでした。
のび小は家からも車で10分ほどで、寮には祖父母の家に泊りにいくくらいの感覚だったことや、先生方も地元の方ばかりで相談もしやすく、チャレンジするにはもってこいの環境でした。
あとは多聞がどんな反応をみせるのか。
3年生の秋に多聞を連れて見学に行ったのは、ランチ会から3年は経っていたと思う。
多聞がどんな反応をみせるのか、
多聞をみて他の児童がどんな反応をみせるのか
不安はなかったといえば噓になるが、それよりも断然楽しみの方が大きかった。
その時の3年生には女の子がひとりだけ。最近お兄ちゃんといっしょに転校してきたばかりの子だった。
多聞もその子も緊張と照れがありながらも、いい距離感で、相性は良さそうだなと感じた。
お住まいを聞くと、なんと僕と妻が新婚生活を送っていた大阪の街(最寄り駅が一緒)だと判明。めちゃくちゃ驚いた。
多聞を置いてけぼりに懐かしい街の話で盛り上がった。
その子は卒業までずっといっしょに過ごし、中学生になって大阪に帰った今でも、多聞は仲良くしている。
1日体験を経て、みんながやさしかったことやわくわくする授業がすっかり気に入り、
続いて1週間体験もやってみたいと本人が希望し、今度は寮生活も一人でチャレンジし、自分で入学を決断しました。
一泊二日体験は、僕もいっしょに過ごすので、まずここまではできるだろうと予想していたが
それでもここからは本当に僕も緊張した。
多聞は新しい学校で、先生や友達とうまくやれるだろうか。。
先生や友達は多聞とうまくコミュニケーションできるだろうか。。
のび小に通うことになれば、きっと寂しいことやしんどいこともあるだろうと思っていました。
その中を自分の力で乗り越えていく試練を与えようとしていたのが私たちの思惑は「見事に軽やかに飛び越えられてしまったな」というのが本音で、それは嬉しい誤算でした。
1週間体験に送り出すとき
僕がなかなか離れられず、いつまでも見守っていると
「お父さん、もう大丈夫だから。帰っていいよ。」と多聞に言われてびっくりしました。
多聞からそんなふうに促されるなんて初めてだったので
本当に驚きました。もうすでに多聞にとってここは「大丈夫な場所」なんだなと思いました。
入学式の日、在校生代表の中原くんの言葉は今でも覚えています。
「きっと新しい場所で不安もあると思います。でも大丈夫です。わたしたちがついています。」
とても心強いメッセージでした。
「こどもは安心安全の環境の中で、もっとも成長する。」そうです。
それは学校の規則とか、先生の指導で作られるものではなく
こどもたちが自らつくっていくものだということを教えてもらいました。
息子はいつも学校の休み時間や、寮での自由時間がとても楽しいと話してくれました。
晩御飯も食べ、お風呂も入り寮の2階にある畳をひいたくつろぎ場所で、友人と一緒にカードゲームをしたり、テレビをみたり、
こどもたちでルールをつくって自由に過ごす体験は貴重で贅沢な時間だったのだろうと思います。
授業も一人一人に合わせた授業を先生方がしてくださり、まるで家庭教師のようでした。
他にも空手や茶道、木工教室、スケート教室、夜みんなでバスに乗って観に行く蛍鑑賞、夏は海でスイカ割りやかき氷、運動会は伝統のうらじゃを自前の法被で踊ったりと盛りだくさんでした。
特に12月のクリスマス会は子供たちがやりたいことを舞台の上で披露するので、進級した4月から「今年のクリスマス会は何やる?」と楽しみにしていました。歌が得意な子はギター演奏しながら歌ったり、ダンスが好きな子は色々な組み合わせでダンスを披露したり、観客席もペンライトで応援して本当に素敵な時間でした。
ただ、寮生活ではひとつ残念なことがあります。
コロナが流行した時に感染対策で、密回避のために子供たちの距離をとる対策として
各自部屋でタブレット使用ができるようになったことが、コロナが終息した今でも継続していることです。
それはやはり寮生活でなければ出来ない貴重な子供たちの身体を使った交流時間をまた元通りにしてほしいと思っています。
また、良いなと感じたことの中のひとつに、卒業生が「どうしようもない、くだらないことで友人と喧嘩になり気まずい状態であっても次の日の朝には絶対に顔を合わせる。すると、なんだかお互い気まずいなぁと感じながらも1日を過ごすとまたなんとなく元の感じに収まっている。」というような事を卒業式で発表している子どもがいましたが、まさにこれこそが生活の中心に学校がある、のび小の醍醐味ではないかと思いました。
他にものび小の掲げる「早寝・早起き・散歩・朝ごはん・掃除」という基本的生活習慣で、入学した時よりも顔色が良くなり意思のある顔つきになる子どもを何人も見かけました。
通ってきている子どもたちは息子のように少人数で屋外学習も多くある、のび小に興味をもって入学する子や、以前の学校がしっくりこなくて来る子など様々な事情で来ていると思いますが、どの子も魅力的な才能を持っています。
そんな子は確かに大人数で団体行動の学校ではその魅力を発揮する機会がなく、心が萎んでしまうだろうと想像できます。
ですから少人数で大らかに見守るのび小は、その魅力をのびのびと発揮して生活できる、子どもにとっては貴重な学校だと思っています。
最後にサポートが必要な息子を受け止めてくださった先生方、寮母の先生、地域の皆さま
あたたかくご指導くださった学園に心から感謝しています。