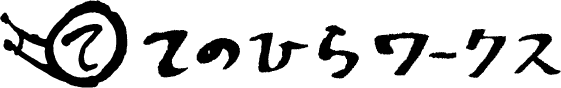吉備高原のびのび小学校のこと part1/2月24日
吉備高原のびのび小学校が来年度(令和7年度)で30周年を迎えます。
30年前といえば、僕が中学3年生の時。
その頃の僕は普通に毎日学校に通い、放課後は夜まで塾通いの日々で、
そこに何の疑問も不安も感じることなかったような気がします。
むしろ塾終わりに友達とコンビニで肉まん食べてくっちゃべっていた、楽しい思い出しか残っていません。
よくいる普通の中学生だったと思います。
まわりの友達も同じようにみえていました。苦しんでいる友達はいたのだろうか。
僕の目には映っていなかっただけで、きっといたのだろうと思います。
不登校というワード自体、そのころ知っていたか怪しい。
不登校が社会問題になったのは80年代で、90年代にはその支援も始まっているようです。
戦後学校教育が始まった1947年から3年後の1950年の文部省の調査では
49年度の長期欠席者(年間30日以上の欠席者)は、小学校で約40万人(出現率4.15%)、中学校で約34万人(同7.6%)。小中合わせて約74万人。
この頃の原因は経済的理由が6割だそうですが、残り4割の30万人は別の理由ということになります。
1960年には「学校恐怖症の研究」という論文が発表されていることから、学校に行きたくない多くの児童がいたことは想像できます。
30年前の1995年の不登校数は
小中合わせて8万人ほど、その2年後には10万人を超えるという
すごい勢いで不登校児童が増えていた時代だったようです。
その時代にのび小は始まり、以来ずっと悩める児童や家族を支え続けています。
中でも全寮制で、児童と家族のように触れあい
日々現場でご指導くださっている先生方には頭が上がりません。
前置きが長くなりましたが
小林家は多聞が4年生から6年生までの3年間。
聞司が1年生から3年生までの3年間。
たっぷりとのびのびと豊かな時間を過ごさせていただきました。
子どもたちにとっても、ぼくら夫婦にとっても、
人生の宝物を頂いたようなそんな時間になったと思っています。
多聞が小学校に就学する時
目の前の円城小学校か、特別支援学校か、答えが出ず悩んでいました。
そんな時、学校相談会に参加して、当時円城小学校の越宗校長先生に出会いました。
僕らの悩みをじっくりと聞いてくださり、
とても丁寧な言葉で優しく、そして冷静に相談に乗って頂きました。
そのうえで「安心して円城小学校へいらしてください。」と。
僕らはその言葉に救われました。
実際、円城小学校では先生方はもちろん
素敵な上級生や同級生にも恵まれて、毎日楽しく通っていたと思います。
のび小へ転校したらどうかと考えることになったのも
この3年間で円城小という素晴らしい環境で
多聞がたくましく健やかに成長したから、
僕の中で多聞をさらに成長させたいという欲が芽生えたからです。
はじめてのび小に行った日のことはいまでも妻とよく話します。
お昼ご飯をいっしょに食べることができる見学会で、地域の方を広く招待しているのですが、
実際には日ごろ交流させてもらっている施設のおじいちゃんおばあちゃんがほとんど。
その日のランチ会も、一般参加は僕ら夫婦ふたりだけでした。
それでも会自体は、とても盛り上がっていて
日頃の交流で信頼関係が築けていることがわかるほど、
子どもたちが自然体でおじいちゃんおばあちゃんと会話したり遊んだりしている姿が
とても印象的でした。
そして、ご飯の前には子供たちの「いただきますのうた」の合唱を聞かせてくれました。
僕はその時の歌声とその姿勢、表情に心を打たれました。とっても心地よい気分でした。
その後は小学生の男の子たちとおしゃべりしながら、
「どこどこ県から来てるよ」とか「道中の車でXジャパンを聞いてるよ」とか
屈託がなくて素敵で、僕が友だちになりたいって思うくらい
楽しいランチタイムを過ごすことができました。
でもその帰り道、
どうしてあんなに輝いた瞳をもった子どもがこの社会の中に居場所がないのだろうと悩みました。
こどもに原因があるのではなく、社会のほうに問題があると考えるほうが自然だと思ったのです。
その年度末、越宗先生が円城小の退任され
のび小に転任されたことを聞きました。
それを知った時、ビビッときたんです。のび小に導かれているような気がしたんです。
part2へつづく。